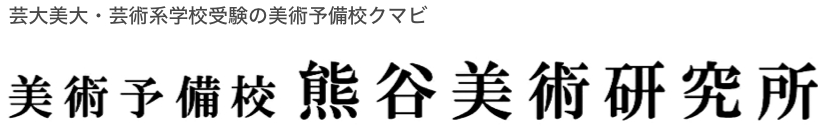芸大美大専門学校生対象

芸大美大や専門学校に在学中の人について
基本がまだ足りなくて学び直したい人や最近はイラストや漫画、クリップスタジオの使い方を習うために有名五美大、専門学校の人が都内からリモートで授業に参加しています。
対面で来る人もいますがだいたいリモートです。
対面で来る人もいますがだいたいリモートです。
基本がまだわからないのでしっかりと学びたい人
最近は芸大美大入試の倍率が下がり、あまり予備校に通わなくても十分合格できる大学が増えています。
かつては受験戦争が激しいため、デッサン力を高めなければ有名5美大以上の大学に合格することは難しく多くの受験生が浪人し、現役生でも相当な実力をつけなければ5美大以上の大学に入れませんでした。
受験戦争が過熱しすぎるあまりに、大学卒業後にデッサン力を必要としない仕事につくつもりの学生の中からは意味なくデッサン力を上げなければならない矛盾した状況に不満の声が上がることもありました。
現在では過剰すぎる受験の熱が下がってきているので意味なくデッサン力を上げなければならないといった状況は珍しくなりました。
ただ今の問題は、社会に出てから「デッサン力が足りないために仕事をもらえない」ということ懸念されることです。
大学に入りやすくなったことは受験で足踏みする必要がなくなった点においては良いことだと言えます。しかし、卒業後にデッサン力が必要になる仕事に携わり、絵を描いたりデザインする仕事を目指す人は自分自身で自分の実力を冷静に評価して今のままで十分に卒業までに力がつくのか判断しなければなりません。
殆どの人の場合、大学や専門学校に入学した後は受験生のように毎日デッサンを描くようなことはないので、デッサン力は大学や専門学校に入った時のまま平行線を辿って大学卒業まで進むことになります。
一部浪人していた時の伸び悩みが大学入学後に花開くケースやコツコツと自宅で真面目に絵を描いて卓越した実力を磨くケースがありますが大学や専門学校の環境やシラバスに頼っているだけで自学自習をしていない場合は毎日6時間以上絵を描いて実力を養っている浪人生並みに実力が上っていることはありません。
学校に在学中は学生生活を謳歌することも大切です。
学生生活を謳歌しながらも、さらに社会にでて仕事をはじめてからもよりよい希望の仕事をし、余暇を持ち楽しむためには自分で時間を作って、通常の授業では改善しない自分の弱点を確認して対策をこうじることも大切です。とはいうものの、芸大美大や専門学校に通いながらダブルスクールでもう一つの学校に通う人は今までにいますが、そうした学生に限り大抵がもともと相当モチベーションの高い学生でした。
芸大美大や専門学校に通いながらクマビに通って本格的に実力を養成できる人は現実的には現状ではあまりいませんが、卒業後に通われる人が多いのでこれを読んだ学生には学生のうちに通って欲しいと思って書いています。
かつては受験戦争が激しいため、デッサン力を高めなければ有名5美大以上の大学に合格することは難しく多くの受験生が浪人し、現役生でも相当な実力をつけなければ5美大以上の大学に入れませんでした。
受験戦争が過熱しすぎるあまりに、大学卒業後にデッサン力を必要としない仕事につくつもりの学生の中からは意味なくデッサン力を上げなければならない矛盾した状況に不満の声が上がることもありました。
現在では過剰すぎる受験の熱が下がってきているので意味なくデッサン力を上げなければならないといった状況は珍しくなりました。
ただ今の問題は、社会に出てから「デッサン力が足りないために仕事をもらえない」ということ懸念されることです。
大学に入りやすくなったことは受験で足踏みする必要がなくなった点においては良いことだと言えます。しかし、卒業後にデッサン力が必要になる仕事に携わり、絵を描いたりデザインする仕事を目指す人は自分自身で自分の実力を冷静に評価して今のままで十分に卒業までに力がつくのか判断しなければなりません。
殆どの人の場合、大学や専門学校に入学した後は受験生のように毎日デッサンを描くようなことはないので、デッサン力は大学や専門学校に入った時のまま平行線を辿って大学卒業まで進むことになります。
一部浪人していた時の伸び悩みが大学入学後に花開くケースやコツコツと自宅で真面目に絵を描いて卓越した実力を磨くケースがありますが大学や専門学校の環境やシラバスに頼っているだけで自学自習をしていない場合は毎日6時間以上絵を描いて実力を養っている浪人生並みに実力が上っていることはありません。
学校に在学中は学生生活を謳歌することも大切です。
学生生活を謳歌しながらも、さらに社会にでて仕事をはじめてからもよりよい希望の仕事をし、余暇を持ち楽しむためには自分で時間を作って、通常の授業では改善しない自分の弱点を確認して対策をこうじることも大切です。とはいうものの、芸大美大や専門学校に通いながらダブルスクールでもう一つの学校に通う人は今までにいますが、そうした学生に限り大抵がもともと相当モチベーションの高い学生でした。
芸大美大や専門学校に通いながらクマビに通って本格的に実力を養成できる人は現実的には現状ではあまりいませんが、卒業後に通われる人が多いのでこれを読んだ学生には学生のうちに通って欲しいと思って書いています。
美術系の学校を出て美術関係の仕事をされている先輩の話
芸大美大/専門学校に通っている時に基本を学び足りなかったり、良くわからなかった人は大勢います。
大学を卒業して学位が取れたり、教員免許が取れたり、パソコンのソフトの使い方を覚え、歴史や業界の実情に詳しくなったとしても、そこまでではまだ十分な実力を身に付けたということにはなりません。
受験でなければ学生の間は実力の差が眼に見える結果として現れることがないので学生の間は問題になりませんが、仕事になれば話は変わります。
煙い話しをするようですが、いざ仕事をはじめた時に必ず直面する問題はスピードとクウォリティーです。
フリーで仕事をする際や会社に就職して会社に美術職が自分1人の場合は納期が問題になります。
自分1人ならまだいいですが、大変な状況は自分以外にライバルがいる場合です。
例えば専門学校を出た人の話しでは、「同僚や先輩に東京芸術大学を卒業した人が大勢いて、自分は会社に入って3年か経つが、自分には絵を描く仕事が周ってこない」ということです。
その方はイタリアに留学までしてしっかりと真面目に専門学校を優秀な成績を卒業しています。しかし、実際の仕事は授業を受けただけではできません。
学校を優秀な成績で卒業しても仕事でまったく実力が通用しないという話しは良く上がります。
習ったことを仕事で使えるようにするには沢山作品を制作して基礎力を仕事で十分使えるレベルにまで養成しておかなければなりません。
学校で単位を取得するのは真面目に授業に参加し、作品を提出すれば可能です。
制作のスピードとその作品のクウォリティーを上げることは単位制の授業を淡々とこなしているだけでできるようになるものではありません。
大学を卒業して学位が取れたり、教員免許が取れたり、パソコンのソフトの使い方を覚え、歴史や業界の実情に詳しくなったとしても、そこまでではまだ十分な実力を身に付けたということにはなりません。
受験でなければ学生の間は実力の差が眼に見える結果として現れることがないので学生の間は問題になりませんが、仕事になれば話は変わります。
煙い話しをするようですが、いざ仕事をはじめた時に必ず直面する問題はスピードとクウォリティーです。
フリーで仕事をする際や会社に就職して会社に美術職が自分1人の場合は納期が問題になります。
自分1人ならまだいいですが、大変な状況は自分以外にライバルがいる場合です。
例えば専門学校を出た人の話しでは、「同僚や先輩に東京芸術大学を卒業した人が大勢いて、自分は会社に入って3年か経つが、自分には絵を描く仕事が周ってこない」ということです。
その方はイタリアに留学までしてしっかりと真面目に専門学校を優秀な成績を卒業しています。しかし、実際の仕事は授業を受けただけではできません。
学校を優秀な成績で卒業しても仕事でまったく実力が通用しないという話しは良く上がります。
習ったことを仕事で使えるようにするには沢山作品を制作して基礎力を仕事で十分使えるレベルにまで養成しておかなければなりません。
学校で単位を取得するのは真面目に授業に参加し、作品を提出すれば可能です。
制作のスピードとその作品のクウォリティーを上げることは単位制の授業を淡々とこなしているだけでできるようになるものではありません。